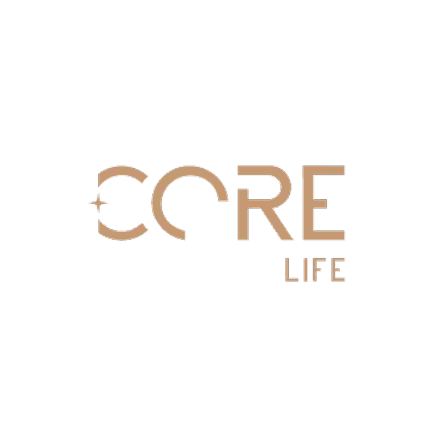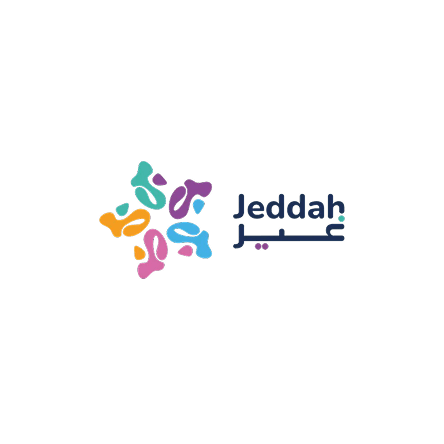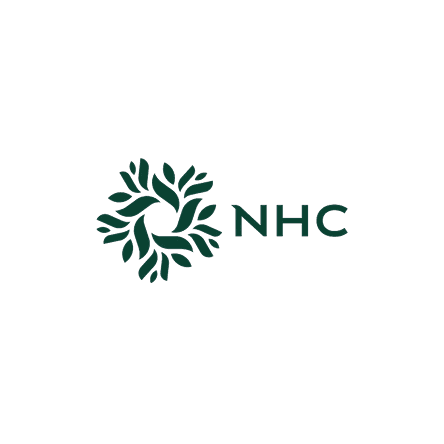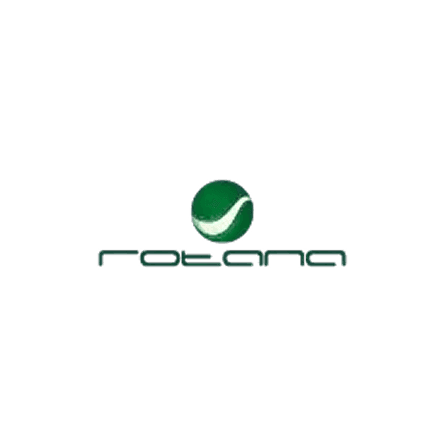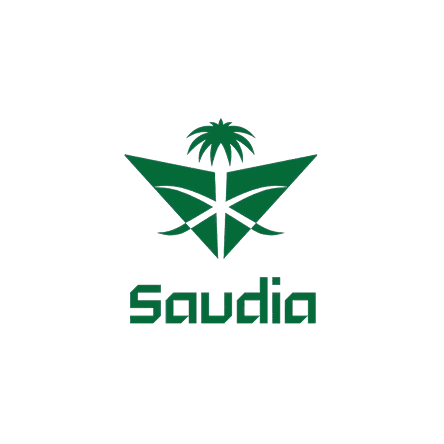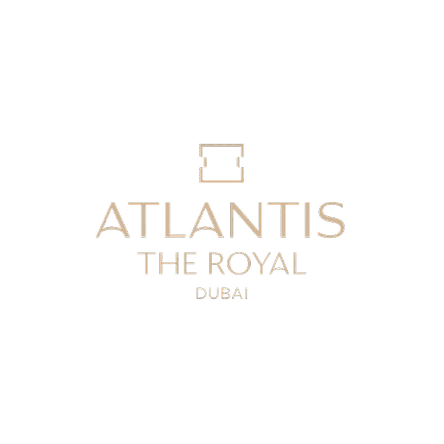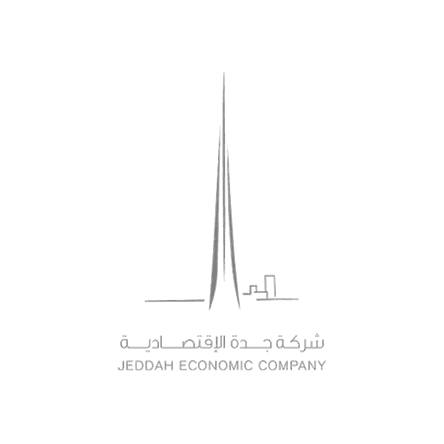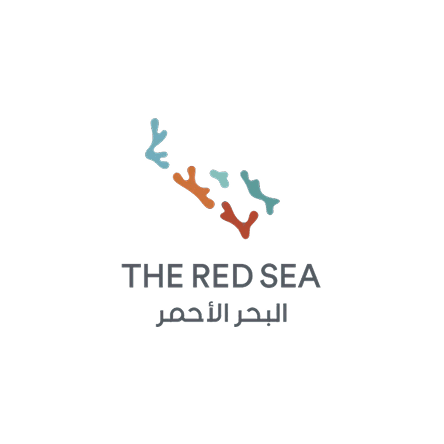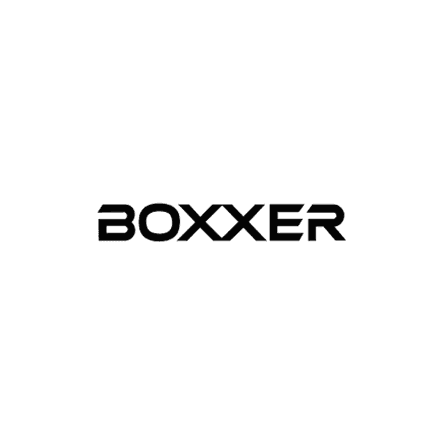Nathaniel Collins, Cristobal Lorente Fight To 12-Round Split Draw In Glasgow
Oct 4, 2025
4 min read
GLASGOW, Scotland – WBC's No. 1-rated featherweight contender Nathaniel Collins lacked guile and more importantly, legs down the stretch during a 12-round split draw with unbeaten European champion Cristobal Lorente during their slow-burning title elim...
GLASGOW, Scotland – Nathaniel Collins was anointed the Next King of Scotland on fight posters preceding his first main event but lacked guile and, more importantly, the legs down the stretch during a 12-round split draw with Cristobal Lorente in their featherweight clash Saturday at Braehead Arena.
Hugues Hellebaut scored the fight 115-113 for Collins, Eric Butel had it 115-113 the other way while Antonio Marogna's 114-114 drawn card meant they couldn't be split after 36 minutes.
Collins (17-0-1, 8 KOs) accepted this performance wasn't good enough to back up his world title aspirations, lamenting an inability to stop the Spaniard after hurting him a few times in the first seven rounds. Both said they were open to an immediate rematch, seeing as this result didn't clarify who was next in line, being a WBC final eliminator after all.
Collins, 29, made quick work of Lee McGregor last time out, but this wasn't a domestic assignment against a former sparring partner. Instead, he was facing an unbeaten European champion in Lorente with a shot at Stephen Fulton's world title being dangled as the reward.
Did he feel pressure leading into this?
"Not really, and the reason is that for long enough I've asked to get in this position," he told BoxingScene before his maiden main event. "I didn't want journeymen at the start, then fought all sorts of domestic fights, said I don't want any more and need to move on. Don't feel you're allowed to feel pressure for something you've asked for. If I didn't think I was ready for this level, to carry or bring back big nights to Scotland, I wouldn't have asked."
Collins quickly got to work scything down Lorente. After the Scotsman's slip had some inside the arena holding their breath at the end of the first minute, Spanish cries of delight came when the visitor countered well with subtle shots landing on the back foot.
Collins connected on two and three-punch flurries as Lorente (20-0-3, 8 KOs) waited, and that was again the case early in round two, Lorente looking unsteady and Collins biding his time as openings would appear to head and body in the final stages of the frame.
The third round was another slow-burning affair, Collins connecting with a big uppercut before they exchanged right hands to finish the stanza - one you'd hope would prompt more back-and-forth action. Instead, they jostled for position at close-range, and Collins kept tagging the Spaniard, albeit with little urgency until they unloaded in the last seconds.
Perhaps buoyed by that brief success, Lorente pitched his best round in the fifth and finally started applying more forward pressure to make Collins work at a heightened pace while catching him clean behind the right hand.
The sixth had more ebbs and flows, though Collins was clearly the aggressor as they exchanged in centre ring with both having bright spells. Collins abandoned defence when hurting Lorente, to his detriment, when he would've been better placed to step back a touch and patiently pick punches to – at the very least – score a knockdown for all his left hands.
Predictably after a busy round, the pace slowed in round seven as Lorente reverted to type, allowing Collins to score with shots at short and mid-range without exerting much energy.
The visitor's best bet was to engage in close quarters and bank on an overconfident Collins, given he was comfortably leading by this stage, though the knockout threat lingered.
Round nine felt like deja vu, Collins flicking out the jab and Lorente firing back furiously with two and three-punch flurries in the latter stages to make an impression on ringside judges naturally consumed by recency bias. Given the crowd noise had quietened too, the visitor did enough to keep Collins honest by this stage and comfortably took his power punches.
Carl Frampton's 87-84 scorecard on DAZN's broadcast was visible on the big screen early in round 10, Lorente winning the last two frames by his judgment and the Spaniard's increased output – combined with less from Collins – made for an interesting finish.
The penultimate round was scrappy and stop-start with clinching aplenty as both looked fatigued, Lorente cut over the eye and Collins needing a push from somewhere – the crowd or a haymaker – to give him that renewed surge of energy he began with earlier.
He saw Josh Taylor motion for him to spin and move sharply at close-range in the final frame, though the bounce in his legs was long gone by this stage. Both corners would've known before the 12th: a gritty encounter and closer than many could have predicted through six rounds. The pair trading furiously in the pocket until the bell exemplified that.
Collins did enough over the 12 rounds to bank a narrow win during a competitive clash, but couldn't complain after failing to match Lorente's inspired second-half showing. It's also more evidence to the contrary for those who criticise hometown decisions in a fight 'The Nightmare' dearly needed to win, with questions emerging from where he goes now.
Analysis
Noticias de combate

Next
Hamzah Sheeraz Won't Wait For Canelo Alvarez, Next Fight Plans Up In The Air
Can you beat Coppinger?
Lock in your fantasy picks on rising stars and title contenders for a shot at $100,000 and exclusive custom boxing merch.

Partners